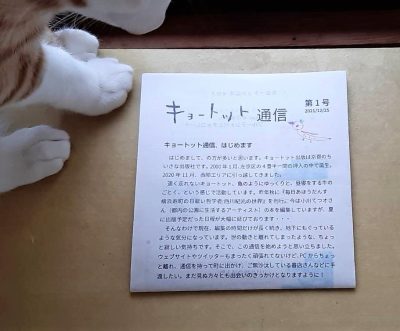第3回 『ファッションを探して』とク・ギョンイのジャージのこと
愛読書との再会
先日、10年前に自分が書いた書評を読み返すことがあった。書評というには未熟で、感想、と言った方がよいのかもしれないが、ひと昔前の私が今の私を励ましてくれるような、ちょっと元気な気持ちになれる文章だった。
取り上げた本は宮谷史子著『ファッションを探して』。疲れがたまったり立ち止まりたいような精神状態のときなど、折に触れては読み返し、そのたびに、もっと自由でいいんだよ、というメッセージを受け取ってきた本だ。今ふたたび、新鮮な気持ちで読み返したくなっている。
そんな愛読書と自分との再会を祝って、まずは10年前に書いた書評を掲載し、そのあと、現在の自分の感想などを記したいと思う。
着ることは、案外、大きなこと
宮谷史子 著『ファッションを探して』(晶文社1992年刊)
※ZINE「かめろん通信」第2号(2012年11月刊)より転載この本が刊行されたのは、1992年。当時20代の私は、著者の飾らない語り口が爽快で、楽しくて、何度も読み返したものだった。もとスタイリストで、ファッション・エディターの著者が、「そもそも着ることって何?」という根源的なことを、まっすぐに問いかけた本だ。
東京は巣鴨のとげぬき地蔵界隈を、思い思いの斬新なファッションで闊歩するおばあさんたち、闘病ののち派手派手なセーターで「青春」を楽しむ81歳のおじいさん、小学校の卒業式にしっかり自己主張して服を選ぶ子供たち、などなど、老若男女の「おしゃれ」が登場する。よくあるファッション雑誌のように、若いとかお金があることを前提に、はたまた人より優位に立ちたい欲望を前提にファッションが語られていない。人生という長いスパンで着ることの楽しさや本質が語られているから、読んでいて気持ちがいいし、元気が湧いてくる。一方、「女の人のファッションって、その人の『役割』によって選別される傾向が、非常に強い」と著者は切り込む。ファッション雑誌にしても、「もうじつにたくみに幾重にも見えない枠」でその縛りに加担している、と。年齢、既婚と未婚、働く働かない・・・そんな枠を強化するのは、「わけのわかんない『常識』だの『良識』」とあるが、それは20年後、2012年の今も、あまり変わっていないかも。それどころか「就活」ファッション、子供の受験や送迎に付き添う母親ファッションなど、昔以上に画一的、または閉鎖的、排他的なにおいがするのは、なぜだろう?
常識や良識。一見もっともらしいけれど、上から見下ろす視線が含まれていたり、「主流的」な立場にとって都合のよい基準をそう呼んだりすることが、ありそうだ。思考停止せず、もう一度自分の着るという行為を、洗い出してみたくなった。
著者は呼びかける。
「自分で自分の役割づくりに精を出して、あんまり着ることを自主規制して欲しくない。そんなこと、その人のあり方とは何の関係もない」「そんな格好が好きだということは、一見自分の役割とちがっていても、どこかでそんな生き方も受け入れていることだ。受け入れるということは、『そんな人の気持もわかるし、話もできるし、友達にもなれる』ということなのだ」「人間の中には、いろんな要素があるのだもの」ああ、その通り! 私は、自分の中のいろんな要素を味わって、楽しんでいるかな? それは自分を尊重することであり、同時に、他者のいろんな要素もありのまま尊重することと、裏表でもあるはずだ。そうなってくると、社会は次のように変貌する。著者の描写があまりに楽しいので、重ねて引用しよう。
「花模様の木綿のワンピースにソックスという、少女みたいな格好で会社に行くバリバリのキャリアウーマン、パンク風のワイルドでドスのきいた専業主婦、ふりふりドレスにリボンが大好きなおばあさん、『あたしってさ、ロック少女だったのよね』なんて、破れたジーンズに安全ピン付きのTシャツで学校に行く先生・・・・・楽しいだろうなあ」
この楽しさは、世界を救う楽しさだ。そうはいっても、という声も聞こえる。誰からも批判されないように、という自主規制がどうしても働く。でも私は、ちょっとずつ変わっていこう。実際、そうした「自由」を意識的に選ぶ人、あるいは自然に選ぶ人が一方で増えている気がする。3・11を経て、これまでの見えない枠を超えていこうと、社会的な運動に参加したり、生き方を見直す人が増えていることと、それはつながっているだろう。
「みんなが、もっともっと好き勝手に、自由に服を着るようになったら、たとえそれが、服やおしゃれの上だけのことだとしても、何かが変わってくるような気もする。
着ることは、小さいようで案外大きなことだから」自由に服を着ることが、社会に風穴をあけていく。久しぶりに読み返し、著者のメッセージが20年前より切実に、生きることとクロスして、私の胸に響いてきた。
女は<特権>が多い?
以上が10年前に書いた文章だ。
『ファッションを探して』は出版社のサイトではずっと品切れとなっている。刊行当時(1992年)はまだバブルの余波が残り、低価格のファストファッションが台頭する以前だ。非正規雇用が増大して、貧困・格差の問題が深刻化する前だから、「今よりは皆、服にお金をかけられて、社会にも余裕があったんだなあ」としみじみ時代を感じる記述も含まれる。一方で、服装の中にあるジェンダーの縛りに疑問をぶつけ、そんな見えない壁を壊してどんどん自由になろう!と女たちに呼びかけているところなどは、時代を先取りしている。
ただ、今回読み返して、女性をとりまく差別への視点は弱いと感じた。
「若い、美しい、そして女であるがゆえにこの社会で得られる特権の、いかに多いことか」という一節がある。そして、周囲から「ぬくぬくと扱われて」「おいしい」思いをした女性が、そのアイデンティティを持ったまま年齢を重ねる末路に警鐘を鳴らす。甘え、傲慢さ、精神的に自立できない不安定さ、今風に言えば「痛い」女。その痛いメンタリティーそのものに批判の矛先を向けている。
批判は一面当たっているかもしれない。しかし、そもそも「若い女」は本当にこの社会で「特権」を得てきただろうか? 30年前、そして10年前には読み過ごしていたが、今回再読して、このくだりには強い違和感が残った。
若さや美しさにゆえに「ぬくぬく」扱われ、お得なことがあるとしても、それは本当に表面的で刹那的なことだ。若さや美しさで品評され、社会からの扱いが変わること自体がルッキズムやエイジズムそのものであり、女性が抑圧の構造に巻き込まれていることに他ならない。
ちなみに「ジェンダーギャップ指数2021」(世界経済フォーラム発表)で日本は156か国中120位、男女格差は先進国中最低レベルだ。国会議員における女性の比率を取り上げると、衆議院でわずか10%と世界水準の半分以下。そんな国で女性が「特権」を得てきた、得ているとは、とても思えない。
自分自身の10代から20代を振り返ると、若いことで多少「ちやほや」されることはあっても、そんなことより、通学・通勤の電車で痴漢に遭うのは日常、大学や職場ではセクハラでひどい目に遭い、また、さまざまな場面で若い女というだけで意思がない者のように軽く扱われる、という辛い経験の方が多かった。
若い女性をとりまく状況は変わっただろうか? 近年では、医学部入試での、長年に渡るとんでもない女子差別も明るみになっている。ファッションの話からそれてしまったが、そうした差別構造の中に女性が生きてきた、生きている、ということに、ここで触れずにはいられない気持ちになった。
ク・ギョンイが気になる
さて、ファッションの話に戻ろう。
私はファッショナブルでもなく、おしゃれさんというわけでも全くない。しかし、毎日の服装と、自分の中に眠った本音というか、「私はこんな気分なんだ!」という心の叫びや呟きのようなものとを、できるだけ一致させたい欲望を持っている。それが自分にとっての「自由に服を着ること」なのかもしれない。
キョートット出版にいる今、幸い、「自由に着ること」をやりやすい環境だ。まずは、ジャージを仕事着に取り入れたい。最近見た韓国ドラマ「調査官ク・ギョンイ」(2021年)、その主人公の服装が妙に気になっている。50歳になったイ・ヨンエ(名作時代劇「宮廷女官チャングムの誓い」でチャングムを演じた人)扮する引きこもりの元警察官ク・ギョンイが履いていた、真っ赤っかなジャージズボンが、目に焼き付いているのだ。
ク・ギョンイはゲーム中毒でアルコール中毒、髪は伸び放題のボサボサで風呂にもあまり入っていない様子。部屋にはゴミが溜まり、廃人のような生活を送っている。過去に夫を自殺に追いやってしまったトラウマを抱え、もがき続けている。服装はいつもスウェットとかジャージやTシャツ。派手な色だったり、変な柄だったり。自暴自棄ゆえのダサくてユルユルな服装なのだが、回想シーンに登場する、警察官姿の彼女やきちんとした白シャツ姿の彼女より、その出で立ちからもれ出る「何かが壊れてさらけ出された感じ」に、私はすごくひきつけられた。
赤いジャージで突き抜けたい
自暴自棄、という言葉を使ったが、正確ではないかもしれない。彼女の服装や態度には、自暴自棄を通り抜け、突き抜けてしまった感じが表れているのだ。自分を放棄したのではない。いらないものは捨ててしまった、ということ。人の視線や評価はどうでもよい、という彼女の境地が、そのラクそうなジャージやスウェット姿に映し出されている、と言ったらいいだろうか。
爆弾のような辛さを抱える彼女の精神は、限界ギリギリの緊張を孕んでいても、どこか一か所風穴があいていて、ヒューヒュー空気がもれている。ゲームとアルコールの力でひたすら現実逃避しているようで、全部が壊れてしまっているわけではなく、大事にしているものは変わっていない。それを彼女は胸の内で密かに守っているようでもある。
彼女は実に美味しそうに酒を飲む。目をつぶって、最後の一滴まで味わい尽くす。焼き肉も好きだ。引きこもりでお金はないが、飲みたい、食べたい欲望にストレートで、忠実。欲望にのまれがちだが、そんな自分を否定していない感じが、彼女の不思議な人間味として伝わってくる。
もちろん、これはテレビドラマであるから、そのファッションはプロのスタイリストによって計算された「ダサかっこ良さ」であることも否定できない。が、そうであっても、彼女の出で立ちから表現されるものに、私は非常に惹かれている。なかなか自分を解放できず、いつまでもモヤモヤし続ける閉塞感を、赤いジャージズボンで突き抜けたい。私はきっと、そう思っている。

(文:石田 光枝)