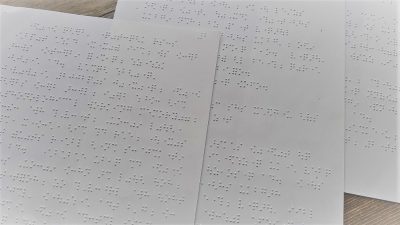点字をめぐる旅<2>
点字と出会いなおした夜
キョートット出版で、点字をテーマにした本を作ろうと動いています。取材の過程を備忘録として綴る連載の2回目は、美術家で点字ユーザーでもある光島貴之さんに登場していただきます。
前回は晴眼者である私が点字に惹かれ、点字を学び始めたことを振り返ってみた。点字との出会いは同時に、点字に対する「墨字(すみじ)」という言葉・概念との出会いであり、自分のマジョリティ―性を強く思い知ることであったことにも触れた。
点字をめぐる旅<1> 墨字(すみじ)の世界観
そもそも、私はなぜ点字が気になったのだろうか。それは2008年、京都市北区紫野、北大路堀川(きたおおじほりかわ)近辺に引っ越したことに始まる。そこは伝統的な織物産業の地、西陣の一角。市バスが通り、地下鉄の駅にも比較的近くて交通の便が良く、社会福祉法人京都ライトハウスや京都府立盲学校など、視覚障害者関連の施設もバスで数分という場所だ。白杖(はくじょう)を使って単独で、あるいはヘルパーさんを伴って歩く視覚障害者の人たちをよく見かける。そんな土地柄が自分に及ぼした影響は大きかった。
それまで、いわゆる障害をもつ人との関わりはあまりなかった。いや、自分から知ろうとしなかったし、どう接してよいのかわからないと勝手に思い、敬遠すらしていたと思う。白杖を手に町を往来する人たちが身近になることで、世界がぐんと押し広げられた気がした。点字への関心にもつながり、前回書いたように点訳ボランティアの養成講座に通うことになった。
今回インタビューを申し込んだ全盲の美術家・光島貴之さんも、この地域にゆかりの深い方だ。生まれ育ったご実家がこのエリアであるし、現在経営されている鍼灸院兼お住まいも同様だ。2020年には鍼灸院から徒歩10ほどのところにアトリエを兼ねた「ギャラリーみつしま Sawa-Tadori」を立ち上げ、創作活動や企画展を意欲的に展開されている。
光島さんのプロフィールをざっと紹介したい。
1954年京都市生まれ。先天的な弱視で、10歳の頃失明。京都府立盲学校から大谷大学文学部哲学科に進学。卒業後の1982年に「みつしま鍼灸院」を開業。鍼灸を生業としながら、1992年頃より粘土造形で創作活動をスタート。1995年から製図用ラインテープとカッティングシートを用いた「さわる絵画」、2012年からは布や金属などの素材を取り入れた「触覚コラージュ」等の新しい手法を探求。近年は釘打ちの手法を取り入れ、より触覚での鑑賞を追求した作品を発表している。
また「ミュージアム・アクセス・ビュー」(2002年設立/京都・関西を中心に活動)の主要メンバーとして、目が見えない・見えにくい人と見える人とが一緒に美術を楽しむ対話鑑賞ツアーやワークショップにも取り組んできた。グループ自体は2022年8月に解散となったが、この活動は「ギャラリーみつしま」においても引き継がれている。
光島さんにインタビューしたいと思ったのは昨年秋、アトリエみつしま企画展「それはまなざしか」(2021年10月1日~10月31日)最終日におけるトークイベント「ながめる音の中で感覚の話をきく」(10月31日 18:00−19:30)に参加して、点字にまつわる光島さんのお話が頭から離れなかったからだ。インタビュー紹介の前に、まずこの時のことを書いておきたい。
話し手は光島さん、そして同じく企画展参加アーティストのひとり、今村遼佑さん。ホームページには「会期後の暗い展示空間の中で、作品や日常にまつわる感覚についての話をします」とあった。秋の夜、「暗い展示空間」というところがワクワクする。2階の消灯された和室会場に入ると、窓越しの薄明りで人の輪郭はわかるくらいの仄暗さ。42畳の大広間は夜の草原のようにも感じられ、圧迫感はなく、心地よい。参加者は思い思いの場所に腰を下ろし、トークが始まった。
光島さんが感覚の話として最初に選んだテーマは、点字。
「僕の好きな点字のかたちを名刺に書いてきました」。名刺が参加者ひとりひとりに配られた。
触ってみると、一角に、点字のふくらみが感じられる。それはある短い言葉を記したもので、好きな言葉というより、その点の配列、つまり「かたち」を光島さんは好きと感じるそうだ。横書き、ほんの2~3センチほどの長さで綴られた点字だ。
私は「あっ」と思った。点字を学んではいても、目が見える自分にとって点字はあくまで目で見て読むものだ。点字に関わりのない人からすると、これは意外なことかもしれない。点字に携わる人は誰もが点字を触って読んでいる、と思われていないだろうか。
しかし、触れて読む=「触読(しょくどく)」は非常に難しい。日常的に点字を使いこなしている視覚障害者は、盲学校や支援施設などで一定の訓練を積み重ね、点字ユーザーとなっている。私の知る限り、晴眼者の点訳ボランティアは視覚を使って読解できれば事が足りるため、触読の技能を求められることはないし、私もその訓練を受けていない。光島さんが好きだという、その短い点字のフレーズを、私は暗闇の中で見ることができないがために、読むことができないのだ。
点字を指で読む/点字を目で読む。本来の点字ユーザーと晴眼者との間にある前提の大きな違いについて、これまであまり意識せず見過ごしていた自分に、暗闇の中、少し茫然となる。指先で点字と向き合うしかない状況に、私は直面している。
光島さんが好きだという点の連なりに、あらためて指を置いてみた。はじめて点字と出会うような気分だ。指先に感覚を集中する。その時点字は、暗い空間の中から私に向かって静かに立ち上がった気がした。左から右へとたどってみる。点が上から下、下から上へと飛んで、音符みたい。不規則に空く小さな間隔が、軽やかなリズムをつくっているようだ。光島さんは、この、風が吹き抜けて点がスキップするようなかたちが好きなのかな・・・。こんなにゆっくりと点字に触るのは、初めてだった。
こうしている間、話題は点字の手触りに及んでいった。薄暗闇の中、落ち着いた、まろやかな光島さんの声が静かに耳に届く。
――点字は何度も読まれるうち、指との摩擦でだんだんすり減っていく。たとえば何人もの人の手で読まれた点字図書館の本や、愛読書の点字。「それはなめらかな手触りに変わっていて、指に心地よくて、好きなんです」。さらに素材の質感も感覚に大きく作用する。普通の点字用紙はツルツルし過ぎていて、好きではない。駅やトイレなどの案内にかかわる点字の素材は金属製だったり樹脂製だったりするが、読んでいて指が痛くなる。一方、さっきの名刺は少しざらっとした質感の厚めの紙で、そこに点字を施した手触りはとても好き――
私には思ってもみない角度からのお話だった。見えている者が墨字で読書するときも、紙の質感など触覚的な要素が影響することは思い当たる。紙が固くてページがめくりにくいとか、薄くてパリパリした触感が面白い、など。しかし、点字ユーザーの場合、読む間、指を紙面にずっと触れて移動させているわけだから、媒体と接触する密度はより濃いとも言える。そうして、点字のすり減り具合に読者の痕跡が残るなんて、推理小説のモチーフにもなりそうだ。
日常的に点字を使う光島さんにとって、点字は情報の媒体といえる。にもかかわらず、文字情報そのものから一歩自由なところで、「この点字の連なりが好き」という感覚が生まれることに、私は小さな驚きを覚えた。
点字の配列を「かたち」としてとらえるその感覚は、光島さんがアーティストであることとも関係しているのだろうか? 点字は墨字(すみじ:点字に対する概念で、視覚的な文字の総称)よりも見た目が幾何学的・記号的という印象なだけに、そこに「好き」が生まれるという光島さんのお話は、少し意外かつ新鮮で、面白い。
好き/嫌い、読みやすい/読みにくい、指先の痛み/心地よさ。もちろん感じ方には個人差があるだろう。光島さんが美術家として粘土やラインテープを扱ってきた指、鍼灸師として他者の身体に触れてきた指の感覚が、触読にも作用しているかもしれない。点字と身体との関係性を観察したり考えたりすることは、触覚文字という独自な文字文化への通路をひらく鍵になりそうだ。
それにしても、名刺の点字は何と書いてあるのか、やはり気になる。点字1マス分の横幅はおよそ5ミリと非常に狭い。暗闇の中、人差し指の先で慎重に見当をつけ、読解にチャレンジする。う~ん。点のふくらみはぼんやりわかるが、その数や配列まではわからない。指を押しつけ過ぎだろうか? 皮膚のごく表面で、点字との間に空気を含ませるように触り直す。すると、少し、点の位置関係がつかめてきた。
・・・「さ」「わ」「や」「か」だ!
トークの途中、光島さんの口からその言葉が「さわやか」だと明かされ、まぐれだとしても記念すべき大当たりとなった。なんだか、熱いものが胸にこみ上げてくる。点字を指で読めた嬉しさを、私はこの先もきっと忘れないだろう。
会場は、もうひとりのトーク出演者、今村遼佑さんの光と音の作品展示の場でもあった。トークの間、光の粒に見える極小の発光体が、畳の境目、少しへこんだすき間のそこかしこに、ふるえるように明滅している。実際に計測した木漏れ日などのデータを、小さな光に変換したもの。音の作品も静かに同時進行していた。カタ・・・。天井に近い方から、密やかな音が聞こえてくる。今度は別の方角から、トン・・・・。木の枝や身の回りの小さなものとモーターを使い、柱や壁を打って音を鳴らす仕掛けのようだ。
暗い空間で、時間の記憶を秘めた微細な光と音とを体感しながら、点字と出会いなおした時間。その感触は、これから続く私の点字へのアプローチを、ずっと後押ししてくれるに違いない。
文:石田光枝[キョートット出版メンバー]