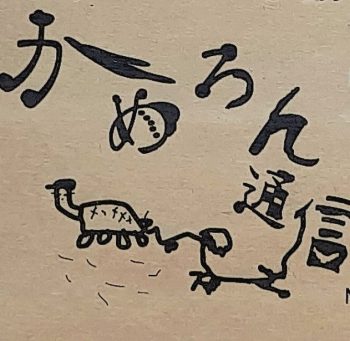沖縄戦について1
このようなやり方で300年の人生を生きていく
現在キョートットでは、16年前に刊行した小川てつオ著『このようなやり方で300年の人生を生きていく あたいのルンルン沖縄一人旅』の改訂版製作に取り組んでいる。
私(小川恭平)が最初にこの旅日記を読んだのは20歳のとき、19歳の著者がクロッキー帳に綴り、ちぎって沖縄から送ってきたものでした。読んで、こんな社会の踏み出し方があるのかと興奮し、勇気をもらいました。私もすぐに沖縄に行ったほどです。「このような生き方」は私の人生の指針にもなったのです。
今回再版をした理由は、学校や親、社会からの抑圧を感じている若い人に「このような生き方」で元気になってほしいというのが一番。したいことをする、したくないことはしないということ。または、自由とか自己決定とかいうこと。
そして、この本のもう一つの魅力は著者の観察眼です。著者の眼を通して沖縄の人々の姿や気持ちがたち現れる。社会や人生の機微が感じられて、心を動かされる。そういう意味ではすべての人生を歩んでいる人に読んでほしい本です。
今回改訂作業は、いつの間にか大改訂となっており、納谷衣美さんという素晴らしい装丁家をパートナーに加え、新たな息吹を加えた本として登場することになります。
新しく加わったものの一つに編注があります。今の目から見て、差別的な表現だ思う部分があり、補うべきだと思いました。また、沖縄戦の叙述についても。
渡嘉敷島に
沖縄戦の本を何冊か読んでわかったことは、私には全く知識が不足しているということだ。「本土の捨て石」「鉄の暴風」「命どう宝」などの言葉は聞いていても、それが意味するところがわかっていなかった。
私は20代の時には合わせて一年くらい沖縄にいた。那覇の泊港から船で一時間少し、慶良間諸島の渡嘉敷島で3ヶ月ほどアルバイトをしたこともある。人口800人くらいで急峻な山がちの島。目の前のビーチは恐ろしくきれいで、夜になると月夜は明るく、月がなければ、天の川から星が落ちるようだった。楽園のようなとこに来たと思った。
でも、向かいの無人島に泳いで渡ると砲弾の残骸がそこらじゅうにあった。不発弾らしきものも。あそこにいくと幽霊が出るといわれる場所もあった。戦争を生き抜いただろうおじい、おばあもその民宿には居たし、うーくい(お盆)の行事にも参加したけど、その島で住民が一カ所にあつまり、330人もの死者を出す集団自決があったことを知らずに3ヶ月を過ごしてしまった。
当時は「集団自決」という言葉は聞いていても、それがどういうことかわかっていなかった。皮肉にもそれを意識するのは、2005年頃から歴史を捏造しようとする人々が、集団自決には日本軍の命令がなかったとか関与がなかったと主張し、『沖縄ノート』(岩波新書、1970年)の著者大江健三郎を訴えたり、教科書を書き換えさせる事態となったことがきっかけだ。事実を捻じ曲げられてはならないと、口を閉ざしていた生存者も新たに証言をはじめた(その証言を読むと、生き残ったものが集団自決について語るということが、いかに大変なことかと想像する)。教科書書き換えに撤回をもとめ、沖縄では11万人が集まる県民大会が開かれた。 当時の私のブログ
「集団自決」では、一人ひとりの命の価値がないものにされる中で、誤った情報や様々な強制の中で住民も死んでいった。家族同士で殺し合ったり、巻き添え等で殺された人も多い。自らの意志で死んだというニュアンスのある「集団自決」より、実態から考えて「強制集団死」と呼ぶほうがよいと言われる。
日本軍は「軍官民共生共死」という方針のもと、「生きて虜囚の辱を受けず」という戦陣訓を住民にも強制し、米軍への投降を許さなかった。
また、米軍は「強姦したりした上、皆殺しにする」という話を信じこまされた(ただし米軍による強姦はあった)。日中戦争等で日本軍は捕虜を虐殺していたので、米軍もそうだと考えるのにはリアリティーがあり、捕まるよりはと「自決」に追い込まれていった。
大江健三郎『沖縄ノート』
大江健三郎『沖縄ノート』を読んでみた。
この本は沖縄「復帰」直前、「復帰」をめぐることを考えながら著された本だった。沖縄と本土のひどい関係、このことをいろいろな人をめぐり考えていく。そして、このひどさは今も全く変わっていない、いやさらにひどくなっていると思い知る。
大江健三郎はその日本や日本人に怒っている。
しかし、その怒る対象に大江自身も含まれるので、逡巡に満ちた文章となっており、何度も「このような日本人ではないところの日本人へと自分を変えることはできないか」と問う。
慶良間諸島・渡嘉敷島の日本軍守備隊長だった赤松氏に対しては予想以上に怒っていた(注:その後、赤松氏の弟が大江氏に対し裁判を起こした)。最終章では、赤松氏の「おりがきたら」<慰霊に(謝罪ではなく!)渡嘉敷島を訪ねたい>という言葉に、激しく怒っている。実際彼は終戦後27年の1970年に渡嘉敷島の戦友を弔いに慰霊祭に訪れた。それが「おりがきたら」ということなのかと怒っている。大日本帝国の将校の意識のまま、27年を過ごしている「このような日本人」について怒っている。

海野福寿・権丙卓『恨 朝鮮人軍夫の沖縄戦』
慶良間諸島には、太平洋戦争時1500人の陸軍秘密部隊が駐留しており、ベニア板製特攻ボート200双を配置していた。このマルレと呼ばれる秘密兵器は、爆弾を積んだボートに人が載って操縦して、敵の艦艇に近づき爆発させるというおぞましいもの。沖縄本島に周辺に集まる米国艦隊を背後から攻撃する予定だった。その隠し壕作りに朝鮮人軍夫や住民が動員されていた。
カライモブックスで買ったままになっていた、海野福寿・権丙卓『恨 朝鮮人軍夫の沖縄戦』(河出書房新社、1987)を読んだ。渡嘉敷島の隣、座間味島や阿嘉島で軍夫をした方の体験談などを主軸に構成されているのだが、なんともすごい本だった。
徴用がいかに強制的なものだったのか、移送中のひどい扱い、那覇大空襲、そして慶良間諸島でのこと。日本人や沖縄の人の体験が苦渋に満ちたものであるに対し、その体験は差別と暴力に満ち、恐ろしくひどいものなのだけど、距離がとれているというか、常軌を逸した日本の軍国主義の中でも、しっかりした価値判断があるというか、何より生き抜くことへの意欲がある。
読んでいて一番衝撃を受けたのは、次のシーンだ。
座間味島。日本兵が特攻ボートを朝鮮人軍夫に海面まで運ばせる。それに飛び乗って「気をつけろ」と一言言って急に爆発させ自決を図り、軍夫を巻き添えにした。どういうことなのか。日本兵は国と一体化したヒロイズムの中、自決をし、朝鮮人軍夫の命をなんとも思っていない。この日本兵の姿は軍国主義教育の一つの完成形なんではないかと思う。これを見た軍夫ら強いショックを受ける。壕に行くと、集団自決のあったあとで、家族で殺し合った惨状を見て、理解できないという気持ちになる。
慶良間諸島は米軍が最初に上陸した島だ。その直後、集団自決で約600人の住民が死んでいる。
渡嘉敷島では一カ所に集まった住民の間で集団自決が起こってしまった。軍から自決の直接命令があったかははっきり確認されていないが、軍命によって集められたのだし、手榴弾がつかわれるなど、日本軍が深く関わったのは間違いない。その後、赤松隊長ら日本軍は島の山中に隠れる。沖縄本島への上陸を始めた米軍はそれをほっておく。赤松隊長らは、住民の家から食料を強奪するだけではなく、米軍に見つかる可能性もあると山中にいた住民の殺害も行い、8月15日終戦後、投降を勧めに来た住民の処刑までしている。
謝花直美『証言 沖縄「集団自決」―慶良間諸島で何が起きたか』(岩波新書)には、「集団自決」についての証言だけでなく、日本兵による住民殺害についての証言も書かれている。赤松隊長が1970年に慰霊に来た時のことも記されており、娘を殺された人は、赤松隊長がまだ生きていたことに呆然とし、父を殺された人は問い詰めている。
「命(ぬち)どう宝」
集団自決から生き残った人の証言で、「命(ぬち)どう宝」(命こそ宝)という言葉に出会いなおした。それは、単に命が大事だということではない。命の価値をゼロに近くされた場面で、命さえあればと生への意思をもつこと。軍国主義にギリギリに抵抗する言葉で、それは実際に人の生死を分ける。
もともとこの言葉は、琉球処分(大日本帝国による琉球王朝の強制合併)を扱った芝居の中で、首里城を明け渡し東京に行く琉球王のセリフから取られている。王は、残る家臣に対して「戦の時代は終わった。命さえあれば」と語る。
母親の「命どぅ宝」という一言で自決を留まり、投降に応じたケースや、渡嘉敷島でも「生きられる間は生きるべきだ」という言葉で、集団自決の現場から抜け出すことができたとの証言もあった。
沖縄戦
沖縄戦は、米軍が1500隻の艦艇で55万人(うち上陸は18万人)を動員し、日本軍11万人と戦い、20万人(うち住民9万4千人)の死者を出した第二次世界大戦での最大規模の戦闘だった。
1945年4月1日、米軍は本島中部西海岸の読谷・嘉手納・北谷に上陸する。そこと日本軍が司令本部を置いた首里との間が、両軍が組織的に戦った激戦地となる。ただし、大日本帝国ははじめから沖縄を本土の捨て石にするつもりだった。日本軍の任務は沖縄県民を守ることではなく、米軍の本土侵攻を遅らせ、時間をかせぐための「戦略的持久戦」を行うことだった。その間、本土決戦に備えて皇居(大本営)を長野県松代の地下につくったり、または敗戦時に国体(天皇制)を残すべく連合軍側と交渉しようとするなどしていた。結局、その時間稼ぎはたんに天皇の存続のためだったといえる。
日本軍11万人のうち、2万数千人は沖縄の一般男性を急きょ集めてつくられた防衛隊や義勇隊で、さらに14才以上の少年約1800人を鉄血勤皇隊、女子生徒約500人を看護要員として動員した。また、朝鮮半島から徴用された軍夫約2800人(1万人とも)が、塹壕堀りや武器の運搬に使役された。130カ所ほどの慰安所を設置し、朝鮮人女性らも使役した。住民も様々な軍役に動員された。
戦闘は首里城地下につくられた日本軍司令部が陥落すれば終わるものと、米軍側も、沖縄の住民も思っていた。それで戦火を逃れ、多くの住民が首里以南の南部地域に避難していた。南部には天然の防空壕として鍾乳洞(ガマ)も多くあった。しかし、日本軍は5月22日に最南部への撤退を決定し、摩文仁に司令部を移動。本島最南部にただ戦争を続けるために軍が逃げてき、壕などを強制的に徴用したため、住民は「鉄の暴風」と呼ばれる砲弾のなかに追い出される事となった。軍民入り乱れていたため、米軍は無差別に海から空から爆撃し、その数は約680万発といわれる。多くの人がその砲弾や、ガマにいて火炎放射器等で殺された。
北から米軍に追い詰められ、摩文仁、米須、山城、荒崎、喜屋武といった最南部の海岸では、手榴弾の自爆や、崖から海に飛び込む等で自殺したり、米軍に投降しようとして日本兵に殺された人も出た。
沖縄県民の死者は12万人といわれ、当時の本島の人口の4分の1が亡くなった。